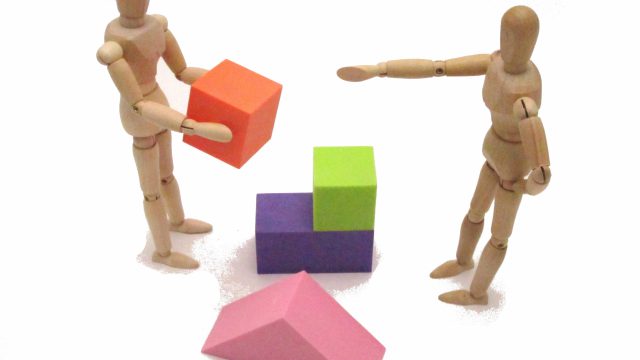建物には基本的に建物買取請求権というのがあります。ただ、条件によっては建物買取請求権の成否が問われるので、事例を参考にするのがおすすめです。
それでは、建物買取請求権の成否について実際に過去にあった判例を見ていきましょう!
一時使用目的の借地について建物買取請求権を行使できるか
今回のケースでは、貸主であるY借主であるAに対して賃借期間を3年に定めて土地を賃貸しました。Aは賃貸した土地上に建物を建築して所有していましたが、Yの承諾を得ることなく建物をXに譲渡し、土地賃借権の譲渡、あるいは転賃を行いました。
XはYに対して借地権の確認を求める訴訟を起こすと共に建物買取請求権を行使しました。
一時使用目的なので建物買取請求権は行使できない
裁判所の見解では、本件の要である本件借地は一時使用目的と認定した上で旧借地法10条に適用されないとのことでした。つまり、今回のケースはあくまで一時使用目的の借地扱いで、他人に譲渡することを目的としたものではありません。
旧借地法9条における一時使用目的の借地は同法10条の適用は大審院も認めている判例であり、今現在でも変更する必要性はありません。
これは基本的に一時使用目的の借地であれば否定できる可能性があるため、今回のケースでXが付け入る隙はどこにもないでしょう。
賃借権の無断譲渡を理由に借地契約が解除された後に賃料相当損害金の不払いがあった場合、建物買取請求権は消滅するか
今回のケースは昭和48年3月5日に起きたもので、貸主であるXは借主であるAにXを初めとする人が共有している土地を賃貸し、Aはその土地上に建物を所有していました。
しかし、Aは同年10月22日にXの承諾を得ずに土地の賃借権と建物をYに勝手に譲渡したのです。これを受け、Xは昭和49年2月26日にAに対して賃借権の無断譲渡を行ったことを理由に1週間以内に原状回復を行わないと、借地契約を解除するとしました。
そして原状回復を行わなかったため、同年3月6日に借地契約を解除しました。
さらにXはAの代理人に対して同年1分以降の賃料不払いを理由に本件借地契約解除を行うものとしました。これを受けたYは建物買取請求権を行使したものの、Xはこれを賃料不払いによる借地契約解除後に行われているので無効だと主張しました。
裁判所ではXの主張を認めたものの、Yはこれを不服として判決が納得いかないことから上告しました。
借地契約の解除もできなければ建物買取請求権も消滅しない
裁判所の判断では、Xの主張が覆る結果になりました。
というのも、確かにXに無断でAが第三者であるYに無断譲渡した場合、Yが所有権を譲渡することをXが認めない間に賃料不払いを理由に借地契約の解除は可能です。
しかし、賃料不払いがなく、賃借権の無断譲渡を理由に借地契約を解除するとXはそれ以降賃料を請求することはできません。また、賃料相当損害金の不払いが発覚しても、それが理由で借地契約を解除する余地がなく、借地契約解除の意思表示が行われていても建物買取請求権は消滅しません。
借地契約の解除はできるものの、それ以上は賃料を請求することもできなければ建物買取請求権が消滅することもないので覚えておきましょう。
借地上の数棟の建物のうち一部が譲渡され、それに伴い借地の一部が無断転賃されたため借地契約全体が解除された場合、譲渡されなかった建物について建物買取請求権が認められるか
今回のケースでは、貸主であるXは借主であるAに数筆の土地を賃貸し、Aは土地上に数棟の建物を建てて所有していました。しかし、Xの承諾を得ずに本件建物以外の建物を第三者に譲渡し、敷地も転賃しました。
これを受けたXは無断転賃を理由に借地契約全体を解除し、Aが亡くなったことで本件建物を相続したYに対して建物収去土地明渡請求訴訟を起こしました。Yは本件建物に対して建物買取請求権を行使しましたが、第一審及び控訴審は建物買取請求権を取得しないとしました。
これを受けたYはこれを不服としたため、上告しました。
違法に確定した事実関係は認められない
そもそも第一審や控訴審が建物買取請求権を取得しないとしたのは、旧借地法10条において建物買取請求権を請求出来る人は借地契約当事者及びその包括承継人以外の第三者、つまり借地権の譲受及び転借にあたって貸主の承諾が得られなかった建物譲受人のみが買取請求権を行使できるものとしているからです。
つまり、その条件を満たしていなかったYが請求権を取得できないとしたのは妥当だと判断されました。
少なくとも借主が誠実な借主であったならば、建物買取請求権が否定されることもなかったかもしれません。
まとめ
何かと第三者が絡む建物買取請求権の問題ですが、基本的に建物買取請求権を行使できる場面は限られているかもしれません。場合によっては貸主が否定される場面もあるとはいえ、多くのケースでは借主が無断で賃借権を譲渡することから始まっているので、それさえなければこのような問題は起きなかったと言えるでしょう。