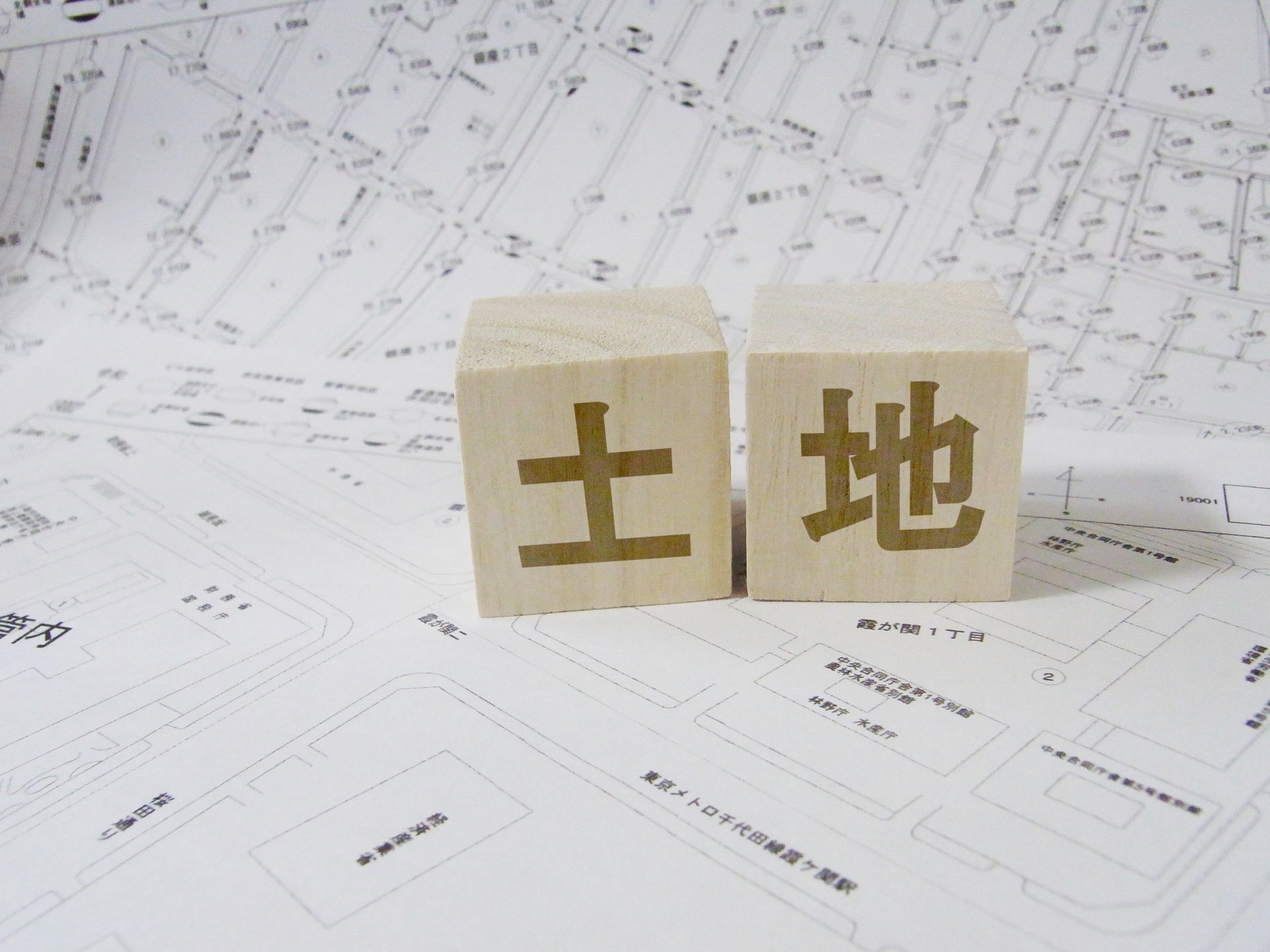譲渡担保契約等における賃借権の譲渡及び転賃については、様々な問題が発生しやすいものです。どのような場合に譲渡及び転賃が認められるのか、これからご説明する実際に過去にあった判例を交えて知っておくことが大切です。
それでは、譲渡担保契約等における賃借権の譲渡・転賃に関する2つの事例ついてご説明しましょう。
借地上の建物が買戻特約付きで第三者に売却された場合、賃借権の譲渡又は転賃があったといえるか
今回のケースでは、貸主のXが借主のY1に対して昭和26年頃から所有する土地を賃借しており、そこへ本件建物を建築して使用していたことから始まります。
昭和33年頃からY1はAから数回ほど運転資金を借りていましたが、昭和34年7月頃に借金をしたいとAに申し出ました。しかし、度重なる運転資金の借り受けに、Aは担保がなければこれ以上貸すことはできないと拒否しました。
そこでY1は本件建物を担保としたため、Aはこれを受けて個人ではなく会社として取引するとしてY2を設立。そして昭和34年7月21日、Y1はXに無断で本件建物をAに235万円で譲渡したのです。この時、Y1とY2の間で締結した売買契約はY1が昭和37年8月31日までに同額で買い戻せる買戻特約付きの売買契約でした。
もちろんXがこれを許すはずがなく、本件建物の譲渡と共に賃借権までもが譲渡されたとし、昭和35年3月11日に本件借地契約の解除と共に本件建物の収去借地の明け渡しを求めて訴訟を起こしました。
ただ、Y1は昭和36年6月1日にY1がY2に対して債務を全額支払ったことで本件建物の所有権がY1に復縁させています。
第一審は本件建物のが譲渡されたことになっているものの、実際は貸付金の担保としてY1を利用したに過ぎず、貸付金が全額弁済された上にY2は今まで一度も本件建物も借地も使用していない状態でした。つまり、賃借権の譲渡及び転賃にはあたらないとしてXの主張を認めず、請求を棄却しました。
それでもXは諦めずに上告しましたが、裁判所は上告も棄却しました。
実際は担保にしただけで譲渡はしていない
裁判所の見解では、本当に譲渡した事実があるのであればXの訴訟や上告は認められるものの、今回のケースでは譲渡の事実はなく、あくまでAから資金を借り受けるための担保として本件建物を利用しているにすぎません。
さらに今回締結した契約は買戻特約付きの売買契約だったため、債務を全額支払えば所有権を復活させることができます。そして問題なく期日までに復縁させているため、Xの主張は認められないということになります。
確かに無断で譲渡したなら問題ですが、そうでない限りは認めらないのも頷けるでしょう。
借地上の建物に譲渡担保の設定がされ、譲渡担保権が実行される前に譲渡担保権者が使用又は収益をした場合、賃借権の譲渡又は転賃があったといえるか
続いてのケースは、貸主であるXが借主であるAに所有している土地を賃貸し、Aは本件土地にAの父であるBの名義で本件建物を所有して居住しているところから始まります。
Aが平成元年2月にCから1300万円を借りる代わりに本件建物を担保とし、2月21日にCに本件建物の譲渡担保とするための譲渡担保権設定契約及び登録申請書類に押印させました。
その後、Cは所有名義をCの妻であるDとする所有者移転登記を行い、Aは本件建物から引っ越しました。しかし、Aは引っ越しする際にXに現状を報告することなく、Cにも連絡が無くなり、行方不明となります。
Yは同年6月10日にEの仲介によって本件建物を賃借しましたが、借地契約書には冒頭にAとCの2人が併記されており、末尾にも貸主A、権利者Cと記載されています。さらに重要事項説明書には本件建物の貸主及び所有者はCと記載され、EはCの代理人と記載されていました。
本来の借地契約はAがXに賃料を支払っていたので、XはAではなくCから賃料が支払われていることを不審に思います。その後、Xは所有名義がDになっていたことを知り、内容証明郵便においてDに本件建物の収去及び借地を明け渡すように命じました。
しかし、CはD名義の所有権移転登記を理由にXの主張を抹消。これを受けてXはAが無断で賃借権を譲渡したことで借地契約を解除し、その間にCはYに対して本件建物の収去及び借地を明け渡すように命じたものの、YはAから建物を賃借していると主張して争いました。
妥当な理由がない限り、借地契約は解除される
まず、本件建物はCが使用収益権を行使しているのでAの借地契約が認められます。そこでYが控訴しましたが、本件建物の所有権が譲渡されているものではないとしてXの請求が棄却されます。
裁判所の見解では、設定された譲渡担保権が行使されていない以上、譲渡担保権が実行されるまでの間は譲渡担保権設定者によって受戻権が行使され、建物所有権が回復できるものとなります。
ただし、今回のケースでは受戻権が行使できる場合であっても賃借権の譲渡及び転賃が行われたものと認められます。実際にAからCに賃借権の譲渡及び転賃がされたとものと認めるのが相当であるものとされたため、Aとの借地契約は解除されますが、賃借権の譲渡及び転賃は認められます。
Aが行方不明になっていても、もはや賃借権の譲渡及び転賃がCに対して行われている以上、たとえ譲渡担保権が実行されていない状況下では認めざるを得ないと言えるでしょう。
まとめ
こうした譲渡担保権における賃借権の譲渡及び転賃は、譲渡ではなく担保にしていただけなのか、そして譲渡担保権が実行されておらず、もはや賃借権の譲渡及び転賃が確定的であるかどうかが争点になるでしょう。
複雑な問題ではありますが、それまでの経緯を紐解いていけば結果は明白になるので、落ち着いて状況を把握することが大切ですね。